ブルーベリーは、甘酸っぱい風味と豊富な栄養価で知られる果実です。小さな粒にアントシアニンやビタミンCなどの健康成分をたっぷり含み、近年では“スーパーフード”として注目されています。
そこで今回は、ブルーベリーの都道府県別の収穫量ランキングや、世界の生産量の比較をしてみたいと思います。
ブルーベリーの収穫量ランキング【都道府県別】
都道府県別収穫量ランキング(上位10県)
このデータは最新情報をもとに農林水産省「特産果樹生産動態等調査」を元にしており、各年度でトップなのは東京都、長野県、群馬県の順となっています。
全体の生産量は2,200 tほどで、上位5県だけで全体の約半分を占めています。
なぜ東京都がトップ?
- 2015年まで約30年にわたり1位だった長野県を、東京都が2015年に逆転し、以降は東京都が常に1位に君臨しています。
- 東京のブルーベリー農園の多くは観光農園形式で、都民にとってアクセスが良く集客しやすいことや、摘み取り+食べ放題サービスが普及しているのが大きな要因です。
補足情報
- 関東圏(東京・群馬・茨城・千葉)が上位席巻。長野を含めて特に関東〜中部地方で多く生産されています。
- 北海道以西では静岡、栃木、愛媛などが上位にありますが、西日本の県はほとんどランク外です。
ブルーベリーの収穫量を前年比較
全国のブルーベリー生産量推移
- 2022年:国内全体で約 2,300 t(2,220〜2,300 tの間)生産されました。
- 2023年:農水省の「2022年産」確報データ発表時期(2025年3月)によると、引き続き約 2,220 t前後とほぼ横ばいで推移。
→ 全国規模では前年比でほとんど増減なし。
上位県の年次別データ比較
主要10都県のデータ(2022 → 2023 年間比較)を以下にまとめました(単位:トン)。
| 順位 | 都道府県 | 2022年 | 2023年 | 差分 | 増減率 |
| 1 | 東京 | 326.0 | 334.0* | +8.0 | +2.5% |
| 2 | 長野 | 252.2 | 256.0* | +3.8 | +1.5% |
| 3 | 群馬 | 236.7 | 231.0* | −5.7 | −2.4% |
| 4 | 茨城 | 203.5 | 204.0* | +0.5 | +0.25% |
| 5 | 千葉 | 108.9 | 109.0* | +0.1 | +0.1% |
| 6 | 北海道 | 90.8 | — | — | — |
| 7 | 埼玉 | 89.2 | — | — | — |
| 8 | 静岡 | 69.3 | — | — | — |
| 9 | 栃木 | 65.6 | — | — | — |
| 10 | 愛媛 | 59.3 | — | — | — |
*2023年は「2022年産」確報データ
- 東京+2.5% 引き続き小幅成長。
- 長野+1.5% 安定した伸び。
- 群馬−2.4% やや減少。
- 茨城・千葉 微増で横ばい傾向。
日本のもも生産量の実態
国内全体の収穫量と推移
- 令和6年産(2024年産)の収穫量は 109,700 t、前産とほぼ同水準(前年並み)です。
- 出荷量は 102,600 tで、前年より約 700 t(+1%)増加しています。
- 結果樹面積は 9,190 ha(前年産比 −70 ha、−1%)、10a当たり収量は 1,190 kgと微増傾向。
- 長期的には、2009年(約 150,000 t)から減少し、2019〜2024年では約 100,000~120,000 tで安定推移。
上位都道府県(2023年産/令和5年産データ)
| 順位 | 都道府県 | 収穫量(t) | 全国シェア |
| 1 | 山梨県 | 33,400 | 約 30.5 % |
| 2 | 福島県 | 約 26,000–28,500 | 約 24–27 % |
| 3 | 長野県 | 約 9,650 | 約 8.8 % |
| 4 | 山形県 | 約 8,800 | 約 8.0 % |
| 5 | 和歌山県/岡山県 | 約 7,240・5,610 | 各 5–6 % |
- 1位の山梨県は全体の約3割を占め、2位福島・3位長野を含めた上位3県で6割以上を占有。
- 4位山形、5位和歌山・岡山も主要産地として存在感あり。
前年との比較(2023年 vs 2024年)
- 全国収穫量はほぼ横ばい(109,500 t → 109,700 t)。
- 出荷量は微増+1%。
- 面積微減だったものの、単位収量(10a当たり)は若干増加傾向。
- 都道府県별の変動情報は確報時に下位まで判明しますが、上位5県で構成比は80%超で安定。
ブルーベリーの世界収穫量ランキング
世界のブルーベリー生産量トップ10(2023年)
2023年の国別生産量は、世界全体で約 1,779,545 トンで、上位10か国で全体の約88%を占めます。
| 順位 | 国名 | 生産量(t) | 世界シェア |
| 1 | 中国 | 563,000 | 約32% |
| 2 | アメリカ合衆国 | 283,000 | 約16% |
| 3 | ペルー | 234,000 | 約13% |
| 4 | チリ | 132,000 | 約7.4% |
| 5 | スペイン | 71,000 | 約4.0% |
| 6 | メキシコ | 67,000 | 約3.8% |
| 7 | カナダ | 63,000 | 約3.5% |
| 8 | ポーランド | 62,000 | 約3.5% |
| 9 | モロッコ | 56,000 | 約3.1% |
| 10 | 南アフリカ | 35,000 | 約2.0% |
上位3国(中国・米国・ペルー)だけで全体の約61%を占める巨大寡占構造です 。
生産面積のグローバル動向
- 世界の栽培面積は2023年に約 267,000 ヘクタール、前年の249,000 haから約7.2%拡大しました。
- 地域別では、ラテンアメリカが最大の113,000 ha(全体の約42%)、アジア太平洋が93,000 ha(35%)、欧州/中東/アフリカ地域が57,000 ha。
アメリカにおける特徴(参考)
- 2023年の米国におけるブルーベリー生産量は約 333.7 百万kg(333,700 t)で世界第1位だったが、中国の圧倒的躍進によりランキングは第2位に後退。
- 2023年の前年比は約−5.2%の減少(2022年比) 。
ブルーベリーの栽培状況と収量向上への課題
ブルーベリーの主な品種
系統(大分類)
| 系統名 | 特徴 | 適した地域 |
| ハイブッシュ系 | 果実が大きく高品質。寒冷地向き。 | 東北・北関東・長野など |
| ラビットアイ系 | 暖地向けで樹勢が強い。果実はやや小粒。 | 関東南部〜西日本 |
| サザンハイブッシュ系 | ハイブッシュの品質+ラビットアイの耐暑性 | 九州・四国・暖地 |
代表的な品種(用途・地域別)
【ハイブッシュ系】
| 品種名 | 特徴 | 収穫時期(目安) |
| デューク | 早生、果実大、収量安定 | 6月中旬〜 |
| スパルタン | 風味豊かで高品質、やや収量少なめ | 6月下旬〜 |
| ブルークロップ | 標準品種。果実大きく、安定性◎ | 7月上旬〜 |
| レイトブルー | 晩生種。遅くまで収穫できる | 8月上旬〜 |
【ラビットアイ系】
| 品種名 | 特徴 | 収穫時期(目安) |
| ティフブルー | 基本品種。果実中粒で豊産 | 7月中旬〜 |
| ブライトウェル | 豊産性。風味よく育てやすい | 7月中旬〜 |
| パウダーブルー | やや晩生、粉を吹いたような美しい果皮 | 7月下旬〜 |
| ホームベル | 古くから日本で普及。収量高い | 7月中旬〜 |
【サザンハイブッシュ系】
| 品種名 | 特徴 | 収穫時期(目安) |
| オニール | 高糖度で香り良し。早生で市場性高い | 5月下旬〜 |
| ミスティ | 収量多く果皮きれい。暖地に最適 | 6月初旬〜 |
| ジュエル | 果実は大きく販売向き。着果性良好 | 6月上旬〜 |
品種選定のポイント
- 気候適応性 寒冷地ならハイブッシュ、暖地はラビットアイ or サザン
- 受粉性 ラビットアイ系は他品種との混植が必要(自家結実性が弱いため)
- 用途 観光農園=粒が大きく見栄え重視/加工=風味・収量重視
- 収穫時期調整 複数品種を組み合わせることで長期間の収穫が可能
現在の栽培状況(日本)
- 作付面積 全国で約1,280〜1,400ha程度(年によって変動)
- 主産地 東京都(観光農園型)、長野県、群馬県、茨城県、千葉県など
- 栽培形態 露地栽培が主流。一部ハウス栽培あり
- 栽培品種
- ハイブッシュ系(寒冷地向け、高品質)
- ラビットアイ系(暖地向け、果実はやや小粒)
- 収穫時期 6月〜8月(地域差あり)
■ 収量向上に向けた課題
土壌・pH管理
- ブルーベリーは酸性土壌(pH4.3〜5.3)を好むため、一般的な農地では条件が合わないことが多い。
- 対策
- ピートモスや硫黄散布で土壌酸性化
- コンテナ栽培(地植えせず培養土で管理)
乾燥と排水の両立
- 水分を好むが過湿にも弱い(根腐れの原因)
- 対策
- 高畝栽培や客土による排水改善
- 自動灌水システムの導入(特に観光農園)
受粉効率の確保
- 自家受粉性はあるが、ミツバチやマルハナバチによる他家受粉で収量向上が見込める。
- 課題
- 蜜源植物不足や気象変動によるハチの活動低下
病害虫・鳥害対策
- 主な病害 炭疽病、疫病、灰色カビ病など
- 鳥害(ヒヨドリ、ムクドリなど)による収穫前被害が深刻
- 対策
- 防鳥ネット・テグス・音響装置
- 病害防除のための適正な剪定と風通し管理
品種選定と適地適作
- 気象条件と品種適性の不一致が収量低下を招く
- 地域ごとの品種適応性や新規品種導入が課題
労働力と収穫体制
- 収穫は手作業中心で、特に観光農園では管理労力が大きい
- 高齢化・人手不足により管理作業が困難化
■ 技術革新による改善例
- 養液栽培(ポット栽培)の導入 pH・水管理がしやすく、単位収量が高い
- 摘み取り型観光農園モデル 収穫人員問題を軽減しつつ、収益性を確保
- ICTによる環境モニタリング 水分センサーや天候予測による潅水制御
■ 世界的な視点での課題と動向(参考)
- ラテンアメリカ(ペルー・メキシコ)では大規模農園+品種改良+輸出体制の最適化により収量拡大
- 一方で、持続可能性(環境負荷・労働条件)への国際的懸念が増加中
- 高温障害、干ばつ、気候変動に対する耐性品種の育成が国際的テーマ
日本産ブルーベリーの将来性
現在の立ち位置と市場環境
国内生産の現状
- 年間生産量 約2,200〜2,300トン(2023年時点)
- 主産地 東京都、長野県、群馬県、茨城県など
- 栽培形態 観光農園(摘み取り)+地元出荷が中心
- 品種 ハイブッシュ系が主流、一部ラビットアイ系やサザンハイブッシュ系も
将来性を支える3つの強み
観光農園ビジネスモデルの確立
- 東京都を筆頭に「摘み取り体験型」の農園が人気
- 農産物としての価格以上の「体験価値」が付加
- 地産地消・直販・6次産業化と相性が良い
健康志向の追い風
- ブルーベリーは「機能性表示食品」や「スーパーフード」として注目される(ポリフェノール・アントシアニン)
- 高齢化社会における「目の健康」など訴求点が明確
- 加工品(ジャム、冷凍、サプリ)への展開余地も大
栽培技術の向上
- 養液栽培やポット栽培による高収量・品質安定
- ICT(潅水制御、気候モニタリング)導入も進行中
- 省力化・自動化によって労働負担を軽減
課題とその克服がカギ
| 課題 | 内容 | 克服の方向性 |
| 労働力不足 | 高齢化・担い手不足 | ICT導入、体験型経営で補完 |
| 鳥害・病害 | ネット・炭疽病・灰色カビなど | 防鳥・防除技術の共有と標準化 |
| 品質のバラつき | 雨・気温・施肥などの影響 | 養液栽培・品種選定の最適化 |
| 輸入品との競合 | 冷凍・生鮮ブルーベリーの輸入増 | 国産の“鮮度・安心・体験”価値で差別化 |
今後の展望と成長戦略
国内消費の拡大
- 冷凍やドライ加工を含めた用途拡大(ヨーグルト、菓子、飲料など)
- 「国産ブルーベリー使用」表示によるプレミアム化
地域ブランド化
- 例 山梨の桃や長野のりんごのように、「〇〇のブルーベリー」というブランド構築
- 産地ごとの品種や香味特性を活かした戦略が有効
輸出展開の可能性(長期的)
- 高品質果実は台湾・東南アジア市場などに需要あり
- 輸送耐性・鮮度保持技術の開発が鍵
ブルーベリーとは?|栄養価・品種・食べ方・特徴まとめ
ブルーベリーとは?
- ツツジ科スノキ属の落葉低木果樹で、北米が原産。
- 樹高は1〜2メートル前後。6〜8月にかけて果実が成熟。
- 甘酸っぱく香りがよい果実で、そのまま食べたり、加工したり多用途に活用される。
栄養価・健康効果
ブルーベリーは“スーパーフード”とされ、次のような栄養素が豊富です。
| 成分 | 働き・効果 |
| アントシアニン | 抗酸化作用・目の疲れ予防・視力サポート |
| ビタミンC | 免疫力向上・美肌効果 |
| 食物繊維 | 腸内環境改善・便通促進 |
| ビタミンE・K | 抗酸化・血管保護作用など |
| マンガン | 骨の形成・代謝補助 |
※カロリー 約50 kcal(100gあたり)と低カロリーでヘルシー。
美味しい食べ方・活用法
| 用途 | 説明 |
| 生食 | 甘酸っぱさと香りをそのまま楽しめる。冷やすとより美味。 |
| ヨーグルト・グラノーラ | 相性抜群。朝食に最適。 |
| スムージー・ジュース | 他のベリーやバナナ、はちみつと合わせて。 |
| ジャム・ソース | 加熱して甘みを引き出す。 |
| 焼き菓子 | マフィン、タルト、チーズケーキに使用されることが多い。 |
| 冷凍保存 | 風味や栄養が保ちやすく、1年中楽しめる。 |
ブルーベリーに関するよくある質問【FAQ】
Q1. ブルーベリーは目に良いの?
A. はい。ブルーベリーに含まれる「アントシアニン」には視覚機能の改善や目の疲労軽減に効果があるとされており、機能性表示食品でも利用されています。
Q2. 生と冷凍で栄養価は違う?
A. ほぼ同じです。冷凍してもアントシアニンやビタミンCなどの主要な成分は大きく損なわれません。用途や保存性に応じて使い分けできます。
Q3. どの季節に食べるのが旬?
A. 6〜8月が旬です。地域によっては5月下旬から収穫される早生品種もあります。旬の時期は、観光農園での摘み取り体験にも最適です。
Q4. 毎日食べても大丈夫?
A. 大丈夫です。ブルーベリーは低カロリーで糖質も適度。1日30〜50g(目安10〜20粒)を日常的に摂取している人も多いです。ただし、大量摂取はお腹が緩くなる場合があります。
Q5. 保存方法は?
A. 冷蔵なら2〜3日、冷凍なら半年〜1年。洗わずにペーパーで包んで密閉容器に入れるのがベスト。食べる直前に水洗いしましょう。
Q6. 家庭でも育てられる?
A. はい、育てやすい果樹のひとつです。鉢植えやプランターでも可能。酸性土壌(pH4.5前後)が必要なので専用培養土が便利。ラビットアイ系やサザンハイブッシュ系は暖地向きで育てやすいです。
Q7. 加工品(ジャム・ドライなど)でも効果はある?
A. ありますが、生に比べると一部栄養素が減少します。とくにアントシアニンは加熱や乾燥で一部減りますが、抗酸化力は残ります。
Q8. ブルーベリーの色素は何由来?
A. アントシアニン系色素です。天然のポリフェノールで、紫~青色の発色が特徴。酸性・アルカリ性で色が変化する性質があります。
Q9. 妊婦や子どもが食べても大丈夫?
A. 問題ありません。自然由来の果実で、ビタミン・ミネラルも豊富。妊婦のビタミンC摂取や、子どものおやつにも適しています。
Q10. ブルーベリーとビルベリーの違いは?
A. ビルベリーはヨーロッパ原産の野生種です。ブルーベリーより小粒で、アントシアニン含有量が多いとされ、主にサプリ原料に使われます。
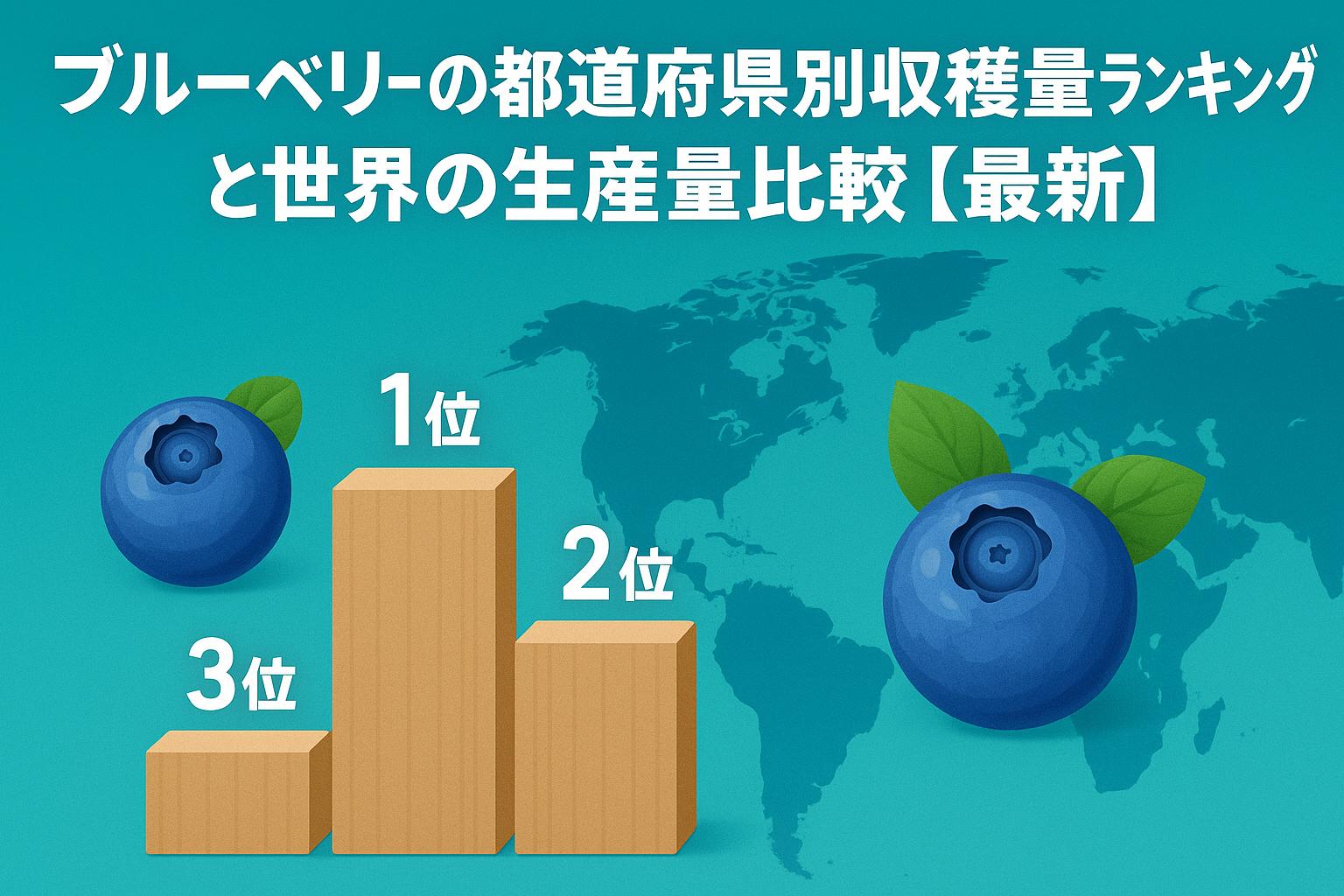


コメント