本記事では、日本国内の柿の収穫量 都道府県ランキングを詳しく解説します。使用するデータは、農林水産省が発表した「令和5年産 作況調査(果樹)」の確報(2024年3月公表)です。都道府県別の収穫量に加えて、前年との比較、世界の主要生産国ランキング、栽培課題や将来展望までを網羅的に紹介します。
柿は秋の代表的な果物で、甘柿と渋柿に大きく分かれ、全国各地で栽培されています。特に奈良県、和歌山県、福岡県などが生産の中心地として知られています。この記事では、最新の収穫量データとともに、柿の現状と未来を読み解いていきます。
柿の収穫量ランキング【都道府県別】
| 順位 | 都道府県 | 収穫量(t) | 全国シェア(%) |
| 1位 | 奈良県 | 33,000 | 20.9% |
| 2位 | 和歌山県 | 28,200 | 17.8% |
| 3位 | 福岡県 | 17,700 | 11.2% |
| 4位 | 岐阜県 | 13,500 | 8.6% |
| 5位 | 山形県 | 11,400 | 7.2% |
| 6位 | 愛媛県 | 9,200 | 5.8% |
| 7位 | 長野県 | 8,100 | 5.1% |
| 8位 | 広島県 | 6,000 | 3.8% |
| 9位 | 静岡県 | 5,300 | 3.3% |
| 10位 | 佐賀県 | 4,800 | 3.0% |
| 合計 | 全国 | 158,400 | 100% |
※出典 農林水産省「作況調査(果樹)令和5年産」確報(2024年3月公表)
奈良県が全国1位の柿産地であり、20%超のシェアを維持しています。続く和歌山県、福岡県を含めた上位3県で約50%を占める構成です。これらの地域では「刀根早生」や「富有」などの品種が中心となっており、温暖で日照時間の長い気候が柿栽培に適しています。
柿の収穫量を前年比較
令和5年産の全国の柿の収穫量は158,400トンで、前年(令和4年産)の165,200トンに比べて約4.1%の減少となりました。以下は、主な産地における前年との比較と変化です。
主な県別の収穫量 前年比(令和5年 vs 令和4年)
- 奈良県 ▲約1,800トン(34,800t → 33,000t)
- 和歌山県 ▲約1,500トン(29,700t → 28,200t)
- 福岡県 ▲約1,000トン(18,700t → 17,700t)
- 岐阜県 ▲約600トン(14,100t → 13,500t)
- 山形県 前年とほぼ同等
全体として、主要産地で軒並み収穫量が減少しています。特に奈良・和歌山・福岡の3県での減少が目立ち、これが全国的な減少傾向の主因となっています。
減少の背景には、開花期の低温や夏場の高温・乾燥、また一部地域での雹や台風被害が影響しています。また、樹勢の弱まりや隔年結果(表裏年)の影響も指摘されており、安定生産の難しさが露呈した一年となりました。
日本の柿生産量の実態
日本国内の柿の年間収穫量は約16万トン前後で推移しており、果物全体の中では中〜上位に位置する生産規模です。以下は代表的な果実との比較です。
| 果物 | 年間収穫量(目安) |
| みかん | 約55万トン |
| りんご | 約70万トン |
| ぶどう | 約16万トン |
| 柿 | 約16万トン |
| もも | 約11万トン |
柿は、温暖な地域を中心に全国的に幅広く栽培されており、甘柿・渋柿の両方が存在する珍しい果実です。甘柿の代表格は「富有(ふゆう)」、渋柿では「平核無(ひらたねなし)」「刀根早生(とねわせ)」などが多く流通しています。
特に奈良県や和歌山県では、甘柿の一大産地として全国流通の中心的役割を担っています。一方で、山形県や福岡県などでは、渋柿を加工用(干し柿)として出荷する割合も多く、用途に応じた多様な供給構造が存在します。
また、収穫後の渋抜き処理や干し柿への加工によって日持ちや付加価値が高まる点も、柿の大きな特長です。
柿の世界収穫量ランキング
以下は、FAO(国際連合食糧農業機関)の統計(2022年時点)に基づく柿の世界主要国の生産量ランキングです。日本の立ち位置を含めて、主な生産国を比較します。
| 順位 | 国名 | 生産量(トン) | 備考 |
| 1位 | 中国 | 約3,000,000 | 圧倒的世界一、全体の7割超 |
| 2位 | 韓国 | 約270,000 | 甘柿・渋柿ともに広く栽培 |
| 3位 | 日本 | 約160,000 | 品質重視、干し柿文化も豊富 |
| 4位 | スペイン | 約130,000 | 欧州最大の輸出国 |
| 5位 | アゼルバイジャン | 約30,000 | 旧ソ連圏の成長市場 |
| 6位 | イタリア | 約25,000 | 地中海性気候で安定生産 |
※出典 FAOSTAT(2022年)
世界最大の柿生産国は中国で、全体の7割以上を占める圧倒的な規模です。主に渋柿系統の加工・輸出向け生産が多く、近年は甘柿品種も増加傾向にあります。
日本は第3位の生産国であり、品質の高さや多様な品種構成が特徴です。特に干し柿文化や贈答用需要、収穫後の加工・選別技術の高さで知られており、中国や韓国とは異なる「高付加価値型」モデルを築いています。
一方、スペインはヨーロッパ市場向けの甘柿輸出で急成長しており、国際競争力の強化が進んでいます。
柿の栽培状況と収量向上への課題
栽培地域と方式
柿は温暖な気候を好む果樹で、日本全国で広く栽培されていますが、特に奈良県・和歌山県・福岡県・岐阜県・山形県などが主要産地として知られます。露地栽培が一般的ですが、一部では防鳥ネットや簡易施設による管理栽培も導入されています。
品種構成と特徴
柿には大きく分けて甘柿と渋柿があり、それぞれに多様な品種が存在します。
- 甘柿 富富有(ふゆう)、早秋、太秋 など
- 渋柿 平核無(ひらたねなし)、刀根早生(とねわせ)、蜂屋柿、会津身不知(みしらず)など
渋柿は脱渋処理や干し柿加工に用いられることが多く、甘柿は生食や贈答品として市場に出回ります。
栽培上の課題
- 気象リスク 高温や干ばつ、秋の長雨、台風などの影響で果実の肥大や糖度が不安定になりやすい。
- 隔年結果 豊作と不作を交互に繰り返す傾向(表年・裏年)があり、安定生産が難しい。
- 病害虫の増加 炭そ病、カメムシ類、果実腐敗などによる品質低下。
- 労働力不足と高齢化 収穫や選別が手作業中心のため、担い手の減少が深刻化。
収量向上と品質維持のための対策
- 整枝・摘果・剪定の適正化による着果安定
- スマート農業の活用(樹勢管理、気象モニタリング、収穫時期予測など)
- 担い手育成・若手就農支援策の強化
- 省力的な脱渋・加工設備の導入
今後の安定供給と品質保持には、技術革新と省力化の両立がカギを握っています。
日本産柿の将来性
日本産の柿は、今後も品質の高さを武器に国内外での需要拡大が期待される果物です。特に地域ブランド化、加工・輸出の強化、スマート農業の導入など、多角的な取り組みが進んでいます。
まず注目されるのが地域ブランド化の深化です。たとえば、奈良県の「刀根早生」、岐阜県の「富有柿」、山形県の「庄内柿」などは、すでに地域名と結びついた高い認知度を誇っています。これらの品種は、贈答用や観光地での直売に強みを持ち、地域経済の中核を担っています。
また、柿は加工適性が高い果実でもあり、干し柿・あんぽ柿・柿酢・スムージー・ジャムなどの6次産業化が進んでいます。特に渋柿は、加工することで一層の価値を生む独自性の高い作物として注目されています。
さらに、アジアを中心とした輸出市場の拡大も期待されています。甘柿は近年、台湾や香港、シンガポールなどで人気が高まっており、日持ちの良い品種や高糖度系統の開発が進行中です。
スマート農業の観点でも、収穫予測AI・気象モニタリング・果実管理アプリなどの活用が徐々に広がっており、高齢化や人手不足に対応した省力型の栽培技術の導入が鍵となっています。
日本産の柿は、「健康」「伝統」「高品質」という価値を兼ね備えた果実として、これからの市場でも一層の注目を集めるでしょう。
柿とは?|栄養価・品種・食べ方・特徴まとめ
柿はカキノキ科カキノキ属に分類される果実で、古くから日本人に親しまれてきた秋の味覚です。原産は東アジアとされ、日本が世界有数の品種数と消費量を誇る柿文化の中心地です。
可食部は果肉で、ビタミンC・βカロテン・カリウム・食物繊維(ペクチン)が豊富に含まれており、抗酸化作用・風邪予防・整腸作用などが期待される健康果実としても知られています。
品種は大きく分けて甘柿と渋柿があり、それぞれの代表品種としては以下のようなものがあります。
- 甘柿 「富有(ふゆう)」「早秋」「太秋(たいしゅう)」など
- 渋柿 「平核無(ひらたねなし)」「刀根早生(とねわせ)」「蜂屋柿」「会津みしらず柿」など
食べ方は、生食用(主に甘柿)のほか、干し柿やあんぽ柿などの加工用(主に渋柿)としても重宝されています。また、最近では柿ジャム、柿サラダ、柿スムージーなどの多様な料理・加工品としての展開も増加中です。
なお、渋柿は渋抜き(アルコール脱渋や乾燥)を行うことで甘くなり、これが日本独自の干し柿文化へとつながっています。
柿に関するよくある質問【FAQ】
Q1 日本の柿の生産量は?
A1 年間の収穫量は約16万トン前後で推移しており、果物の中では中〜上位の規模を持つ品目です。
Q2 柿の主な生産地は?
A2 奈良県・和歌山県・福岡県が上位を占めており、全国シェアの半数以上をこの3県で占めています。
Q3 柿の収穫量は前年と比べてどうか?
A3 令和5年産の収穫量は前年より約4.1%減少しました。気象条件や隔年結果の影響が要因です。
Q4 世界一の柿生産国はどこ?
A4 中国が圧倒的な世界一で、年間300万トン以上を生産しています。世界全体の7割超を占めます。
Q5 日本は柿を輸入しているのか?
A5 基本的に輸入量は非常に少なく、ほぼ国産で自給自足されています。一部、加工品や乾燥柿の輸入はあります。
Q6 柿の価格はどのくらいか?
A6 生食用の柿は1個100〜200円程度が相場で、ブランド品や大玉は1個300円以上になることもあります。干し柿はさらに高価格帯になります。
Q7 柿は家庭で栽培できるか?
A7 はい、比較的育てやすい果樹で、家庭菜園でも人気があります。広い庭があれば地植え、狭いスペースなら鉢植えの矮性品種も可能です。

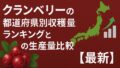
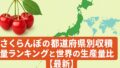
コメント