いよかんは、冬から春にかけて旬を迎える柑橘類のひとつで、ほどよい酸味と甘み、爽やかな香りが特徴です。愛媛県を中心に栽培され、日本の食卓に親しまれています。皮がむきやすく、果肉はジューシーで食べやすいため、幅広い世代に好まれています。
そこで今回は、いよかんの都道府県別収穫量ランキングと、世界の生産量を比較したいと思います。
いよかんとは?基本情報と特徴
いよかん(伊予柑)は、明治時代末期に山口県で偶発実生として発見され、その後愛媛県(旧伊予国)で広く栽培されるようになった日本原産の柑橘類です。 正式名称は「イヨカン」、英語では「Iyokan orange」と表記されることもあります。
- 学名 Citrus × iyo
- 分類 ミカン科・カンキツ属(雑柑の一種)
- 系譜 夏橙(なつだいだい)× 不明(文旦系と考えられる)
特徴・魅力
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 香り | 非常に芳醇。温州みかんやネーブルより華やか。 |
| 味 | 甘味・酸味のバランスが良く、爽やかで飽きが来ない。 |
| 旬 | 1月~3月(最盛期は2月) |
| サイズ | 200~300gほど。みかんより大きく、手のひらサイズ。 |
主な品種と系統
宮内いよかん(みやうちいよかん)
- 現在もっとも多く流通している主力品種(実質スタンダード)
- 1920年(大正9年)頃に愛媛県今治市宮内で発見された枝変わり品種
- 果皮はやや薄くてむきやすく、糖度・酸味のバランスが良い
- 収穫期:1月上旬〜中旬、出荷は2月〜3月が最盛
大谷いよかん(おおたにいよかん)
- 愛媛県松山市の大谷地区で発見された枝変わり
- 宮内いよかんより果実がやや大きめで、果皮も厚め
- 甘味がやや強く、果肉がやわらかい
- 生産量は少なく、主に地場流通向け
元祖いよかん(在来種)
- 初代の伊予柑(山口県萩市で発見→愛媛県松山で栽培)
- 宮内いよかん以前に栽培されていたが、現在はほとんど見られない
- 果皮が厚く、酸味が強めでやや粗野な印象がある
系統としての特徴比較
| 品種名 | 発見地 | 果実特徴 | 収穫時期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 宮内いよかん | 愛媛・今治市 | 中玉・甘酸のバランス良 | 1月上旬〜中旬 | 国内流通の主力系統 |
| 大谷いよかん | 愛媛・松山市 | やや大きく甘め | 1月中旬〜下旬 | ごく一部の産地限定 |
| 元祖いよかん | 山口・萩市 | 厚皮・酸味強め | 1月中旬以降 | 現在はほぼ絶滅状態 |
都道府県別生産量ランキング
| 順位 | 都道府県 | 2018年生産量・シェア※1 | 2022年生産量・シェア※2 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 愛媛県 | 26,293 t(92.3 %) | 19,300 t(92 %) |
| 2位 | 和歌山県 | 687.8 t(2.4 %) | —(概算シェア ≈2.4 %) |
| 3位 | 佐賀県 | 647.1 t(2.3 %) | —(概算シェア ≈2.3 %) |
| 4位 | 山口県 | 176.9 t(0.6 %) | — |
| 5位 | 静岡県 | 173.3 t(0.6 %) | — |
| 6位 | 鹿児島県 | 136.4 t(0.5 %) | — |
| 7位 | 香川県 | 93.4 t(0.3 %) | — |
| 8位 | 広島県 | 85.5 t(0.3 %) | — |
| 9位 | 熊本県 | 58.2 t(0.2 %) | — |
| 10位 | 長崎県 | 36.6 t(0.1 %) | — |
※1 2018年データは、全国合計28,495.2 t ※2 2022年データは、愛媛県全体で約21,000 t(うち19,300 tが愛媛〈92 %〉)
愛媛県の圧倒的優位性
- 圧倒的第1位:2018年の26,293 t(全国シェア92.3 %)、2022年にも19,300 t(92 %)と首位を独走
- おもな産地:松山市、今治市、八幡浜市
- 地理分布:松山市(中予)・北条・中島などが中心、南予地域でも宇和島・八幡浜などで生産が広がる
和歌山県・佐賀県
- 和歌山県 687.8 t(2.4 %)
- 佐賀県 647.1 t(2.3 %)
上位3県で国内の約97%をカバーしています。
生産量の推移と変化
全国推移(収穫量)
- 2021年 栽培面積 約1,709 ha、収穫量 約23,575 t(うち愛媛県約21,611 t)
- 2022年 全国約21,000 t(愛媛県が19,300 t=シェアおよそ92 %)
愛媛県の収穫量推移詳細
| 年度 | 栽培面積(ha) | 伊予柑収穫量(t) |
|---|---|---|
| 平成29年(2017) | 約1,140 | 28,070 |
| 平成30年(2018) | — | 27,479 |
| 令和元年(2019) | — | 25,640 |
| 令和2年(2020) | — | 23,468 |
| 令和3年(2021) | 約900 | 21,611 |
| 令和4年(2022) | 約800前後 | 19,349 |
→ 過去6年で約45%の減少。特に2021~2022年で▲2,262 t(‑10.5%)と急減
前年比較 2022年 vs 2021年
- 全国では -約2,575 t、率にして -11 %程度
- 愛媛県に限れば -約2,311 t、約 -11 %
栽培面積・収穫量ともに減少傾向が続いています。
減少の背景と要因
高付加価値品種への転作
- 「紅まどんな」「せとか」「甘平」「河内晩柑」などの人気品種に作付け替えが進行中
- 収穫量が減少した主因として、中晩柑類(紅まどんな・甘平・せとかなど)への作付替えによる影響が愛媛県内で進んでいる点が挙げられます
収益性・価格競争力の低下
- 市場価格上では一時優位だったが近年は相対的に下落、栽培意欲が落ちている
- 伊予柑は単価が安定しないため生産者の関心が低下
栽培面積の縮小
全体的果樹農家の減少傾向に伴い、伊予柑も例外でなく農地減少の影響を受けている
その他の要因
- 栽培樹の老木化:長年の栽培で樹が老齢化しており、収量や品質に悪影響
- 労働力不足と高齢化:柑橘農家の高齢化と人手不足により、収穫・管理作業が困難
- 病害虫・天候リスク:カンキツグリーニング病などの病害や、カメムシ被害、台風や凍害による果実落下
世界でのいよかん生産状況
日本特有の柑橘である伊予柑(いよかん)は、世界規模での統一的な生産統計が存在しないため、国際ランキングとしてまとめることはできません。
世界での生産状況
- 伊予柑は日本のローカル品種であり、主な生産地は国内(特に愛媛県など)に限られています
- 英語版ウィキペディアによると、日本国内で伊予柑の生産量の90%以上が愛媛県に集中しており、輸出向けなどの「世界生産」と呼べる生産形態はほぼ存在しません
日本国内での位置づけ
- 日本では、温州みかん(Satsuma mandarin)に次いで全国で第2位の柑橘生産量を誇ります
- いわゆる「世界柑橘市場」として集計されるオレンジやレモン、グレープフルーツなどに比べると、伊予柑は商業的規模が非常に小さく、世界統計へ反映されません
世界の柑橘生産との比較
- 世界全体の柑橘生産量(オレンジ・レモン・グレープフルーツなどを含む総量)は、2020年に約1億4,420万トン(144百万トン)に達しています
- 伊予柑の生産量は日本国内で通常2万〜3万トン程度であり、これは世界規模では1万分の1以下の非常に小さな規模にとどまります
栽培状況と収量向上への課題
収量向上に向けた課題と対策
栽培樹の老木化と更新の遅れ
- 課題:長年の栽培で樹が老齢化しており、収量や品質に悪影響
- 対策:計画的な樹の更新(植え替え)、台木更新技術の導入
病害虫・天候リスク
- 課題:カンキツグリーニング病などの病害や、カメムシ被害、台風や凍害による果実落下も深刻
- 対策:被覆資材の導入、防風ネット、減農薬の予防技術
他品種との競合(作付転換)
- 課題:「紅まどんな」「甘平」「せとか」など高単価中晩柑への転換が進行、伊予柑は単価が安定しないため生産者の関心が低下
- 対策:
- 伊予柑のブランド再評価
- 加工品・輸出向け用途開発など販売戦略の多様化
労働力不足と高齢化
- 課題:柑橘農家の高齢化と人手不足により、収穫・管理作業が困難
- 対策:
- 省力化機械(自動選果機、枝剪定補助機)導入
- スマート農業(AI・IoT)による管理の効率化
土壌・肥培管理の技術格差
- 課題:栽培者間での知識・技術のばらつきあり
- 対策:JA・県農業技術センターによる栽培指導の強化
愛媛県の主な施策
- 「かんきつ王国復活プロジェクト」 高付加価値品種とともに伊予柑の栽培継続支援を明記
- スマート農業実証実験(ドローン散布、遠隔水管理)
- 若手就農者支援事業 伊予柑を含む中晩柑での就農モデル創出
日本産いよかんの将来性
現状の課題
生産量の減少
- 伊予柑の生産量は過去10年で大幅に減少
- 愛媛県 2012年 約30,000t → 2022年 約19,000t(▲35%以上)
- 主因
- 他品種(甘平・紅まどんな・せとかなど)への作付転換
- 価格の伸び悩み・収益性の低下
- 樹の老化・栽培者の高齢化
市場価値の相対的低下
- 食味や香りは高評価だが、中晩柑としての「強い個性」に欠ける
- 高単価品種に比べて魅力的なブランド化が進んでいない
輸出・加工面での展開力不足
- 海外での認知度が低く、輸出量も微少
- 果皮が厚く剥きにくいという難点から、簡便志向の国内消費ともややミスマッチ
将来性と可能性
独自の香り・バランスの良い味わい
- 温州みかんにはない爽やかな香りと甘味+酸味のバランスは根強いファンが存在
- 「香り柑橘」として再ブランディングの余地あり
加工用途への展開
- 果汁やジャム、ゼリー、リキュール、クラフトビール等への利用可能性
- 加工用原料としてなら、果皮の厚さや剥きにくさがむしろ利点
輸出のポテンシャル(アジア圏など)
- 台湾、香港、シンガポールでは日本産柑橘が人気
- 「IYOKAN」という名前の響きやオレンジ色の果実は海外向けに展開可能
スマート農業・省力化導入の余地
- 伊予柑の栽培は収穫期が冬~春で労働分散に向く
- 労働力不足の中、省力栽培やロボット化との相性がよい
今後の方向性(提言)
| 観点 | 展望・戦略 |
|---|---|
| ブランド再構築 | 「伊予柑=香り柑橘」「和製グレープフルーツ」など個性強化 |
| 加工展開 | 果汁・スイーツ・酒類など差別化商品開発 |
| 輸出振興 | 台湾・香港など富裕層マーケットでのPR |
| 栽培支援 | 若手農家向けの省力技術・苗木補助の強化 |
栄養価と健康効果
栄養価(100gあたり)
| 成分 | 含有量 | 特徴 |
|---|---|---|
| エネルギー | 約46 kcal | 低カロリーでヘルシー |
| ビタミンC | 約35 mg | 免疫力・美肌に◎(1日の約35%) |
| 食物繊維 | 約1.3 g | 整腸作用に効果的 |
| クエン酸 | 多く含む | 疲労回復、食欲増進に |
| β-カロテン | 微量 | 抗酸化作用あり |
- 水分が90%以上を占め、みずみずしくジューシー
- ビタミンC・クエン酸が豊富で、風邪予防・美容・疲労回復に優れる
食べ方・利用方法
生食(定番)
- 手では剥きづらいため、包丁でカットして食べるのが一般的
- 内袋(じょうのう)はやや厚めなので、果肉だけ食べるのが食べやすい
加工品
- 果汁 ジュース、ゼリー、サイダー、ドレッシングなど
- 果皮 マーマレード、ピール菓子、リキュール原料に
例 伊予柑ポン酢、伊予柑ビール、伊予柑ジャム
よくある質問【FAQ】
Q1. いよかんはどこの果物ですか?
A. 日本で生まれた柑橘で、山口県で発見され、愛媛県で広く普及しました。現在は全国生産量の90%以上が愛媛県産です。
Q2. いよかんの旬はいつですか?
A. 収穫は1月〜2月ごろで、出荷・流通は1月下旬〜3月が最盛期です。特に2月が「食べ頃」とされます。
Q3. 温州みかんやせとかとの違いは?
A. 温州みかん 皮がむきやすく甘み主体、酸味は少なめ。 いよかん 香りが豊かで甘味と酸味のバランスが良い。 せとか とろけるような食感で非常に甘い、高級系統。 → いよかんは「香り」や「爽やかな酸味」が特長です。
Q4. いよかんの皮は食べられますか?
A. 生食では厚くて苦みがあるため通常は食べませんが、マーマレードや砂糖漬け(ピール)など加工すれば美味しく食べられます。
Q5. ビタミンCは多いですか?
A. 100g中に約35mgのビタミンCが含まれており、1日推奨量(成人:約100mg)の約1/3を補えます。
Q6. どうやって食べるのが正しいの?
A. 手ではむきにくいため、包丁でカットして食べるのが一般的。スライスくし形切り房から果肉だけを取り出す「スマイルカット」などもおすすめです。
Q7. いよかんは外国にもある?
A. ほぼ日本国内限定の柑橘で、海外での栽培はほとんどありません。輸出も一部のアジア圏に限られています。
Q8. 保存方法は?
A. 風通しの良い冷暗所で1~2週間保存可能。長期保存には新聞紙に包んで冷蔵庫の野菜室へ。乾燥を避け、腐敗果が出たらすぐ除去するのがポイント。
Q9. どんな加工品がありますか?
A. いよかんジャム、いよかんゼリー、いよかんサイダー、ピールチョコ、マーマレード、地ビールや焼酎のフレーバーにも利用されます。
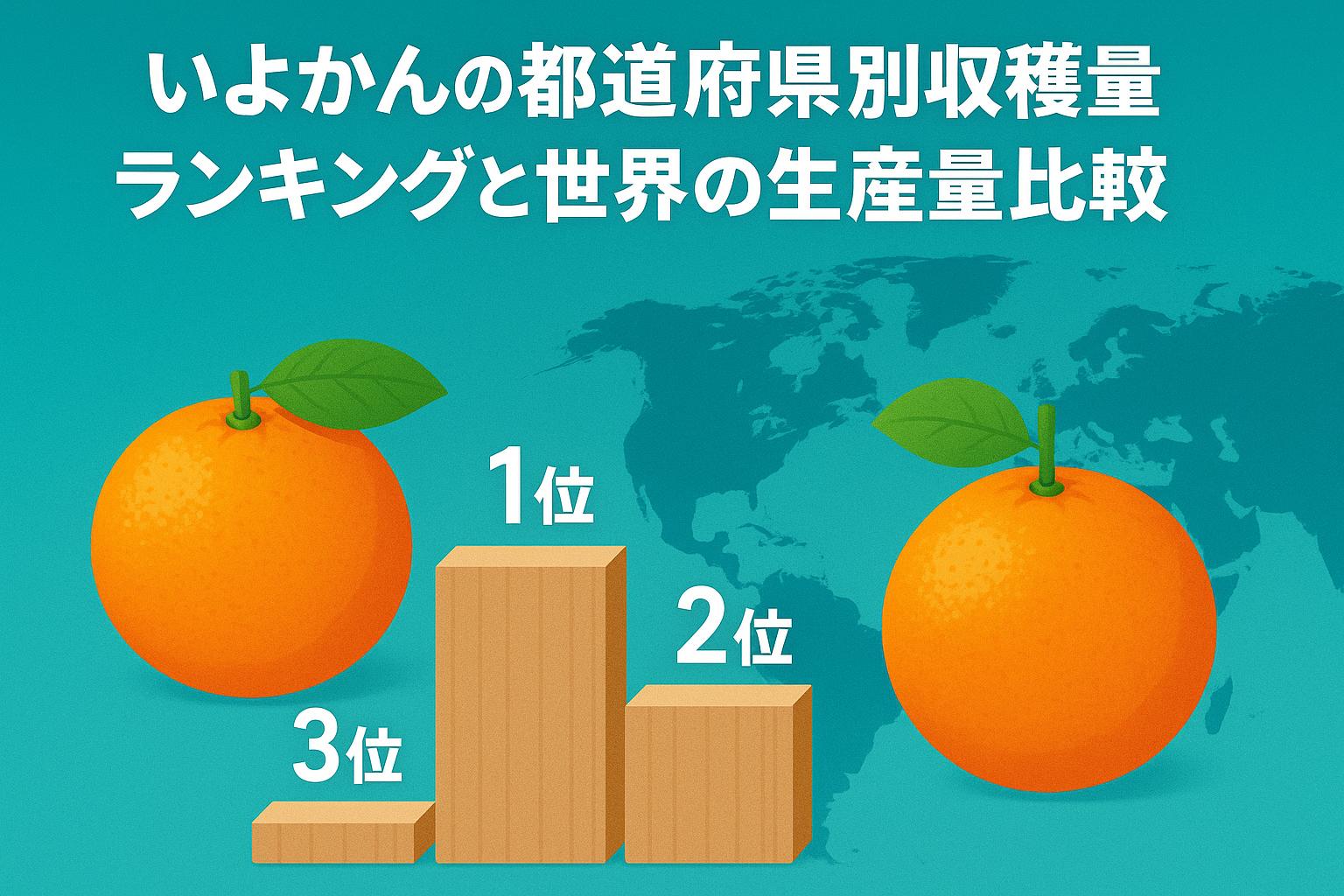


コメント